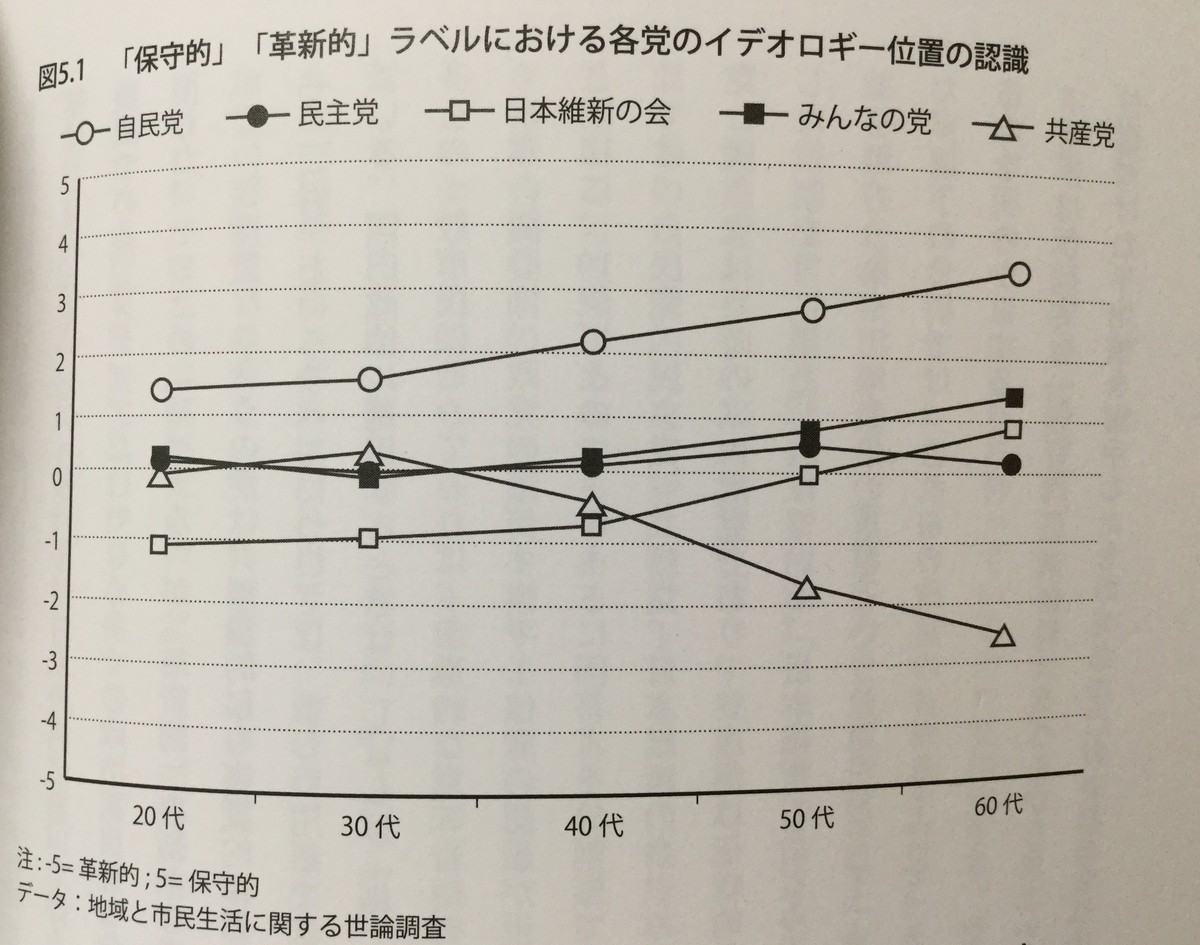副題が「協力と均衡の地政学」となっているので、著者流の国際情勢分析かと思いましたが、内容としてはJICA(国際協力機構)の理事長としての仕事をまとめたエッセイとなっています。
ただし、著者は政治学者でありながら日本の国連次席大使も務めたことがあり、さらに安保法制懇の座長代理として安保法制に関する議論を取りまとめるなど、政治色の強い人物でもあります。
この本を読むと、そうした現在の官邸に近い外交方針と、著者の個人的な関心が垣間見えて、そのあたりにもこの本の面白さはあります。
また、以下に示す目次からもわかるように、途上国を中心に本当にいろいろな国を訪れており、まさに「大国抜きの世界地図」といった趣になっています。
目次は以下の通り。
序章 自由で開かれたインド太平洋構想――日本の生命線
第1章 ロシアとその隣国たち――独立心と思慮深さを学ぶ
ジョージア、アルメニア、ウクライナ、トルコ、フィンランド、バルト三国第2章 フロンティアとしてのアフリカ――中国の影と向き合う
ウガンダ、アルジェリア、南スーダン、エジプト、ザンビア、マラウイ第3章 遠くて近い中南米――絆を強化するために
ブラジル、コロンビア第4章 「海洋の自由」と南太平洋――親密な関係を維持できるか
パプア・ニューギニア、フィジー、サモア第5章 揺れるアジア――独裁と民主主義の狭間で
ミャンマー、ベトナム、東ティモール、タジキスタン終章 世界地図の中を生きる日本人
第1章ではロシアの周辺諸国がとり上げられています。基本的にロシアという大国に圧迫を受けた歴史がある、あるいは現在進行系で圧迫を受けている国ですが、だからこそ自国のアイデンティティを大切にしています。
著者はひるがえって日本はどうかと問いかけます。
もし、日本人が世界へ離散するようなことがあったらアイデンティティの核となるものはなんだろう? と問い、「日本語」と「皇室」をその候補としてあげ、皇室改革の必要性を訴えています(46p)。
最後に日ロ関係を論じていますが、北方領土問題に関しては「経済力をテコに領土問題を解決するのは、なかなか難しいだろう」(85p)と見ています。そして次のように締めくくっています。
将来、ロシアにとって真に重要な問題は、ロシアの人口がさらに減る中で、中国の圧力にどう対応するかということである。中国のジュニア・パートナーとなる道を選ぶのか、それとも拒むのか、難しい時期がもうすぐ来るだろう。その時、日本は重要なパートナーたりうる国である。その時まで、焦らず距離を置きつつ、つきあうのがよいように思う。(85p)
第2章はアフリカ。ここではウガンダに逃れてきた南スーダンからの難民への職業訓練や米作の普及などの支援や、エジプトでの日本式小学校の話が興味深いですね。エジプトのエルシーシ(シシ)大統領は、規律ある行動を非常に重視しており、日本人の規律ある行動の秘訣として小学校教育を見ているそうです。
マラウイ訪問についての文章には、RCT(ランダム化比較試験)が全盛となっている欧米の援助に対する、日本独自の「国際協力」のあり方が次のように書かれています。
水も電気もないところで日本人が活躍している。彼らにとって、それは人生で大きな経験になるだろうし、また現地の人が日本人は立派だと思ってくれる。それで十分ナノではないだろうか。日本では援助といわず、協力という。それは相手の立場に立って貢献しようということである。それだけでなく、協力によって、こちらにも得るところが多いということなのだろう。(119p)
あと、ここでは従軍慰安婦の話や南スーダンのPKOについても触れており、このあたりは著者の政治的立場が出ている部分と言えるでしょう。
第3章は中南米。とり上げられているのはブラジルとコロンビアですが、JICAはもともと日本人の移民を支援する組織だったこともあって、日系人の活躍などが触れられています。
ただし、現在の日本政府と日系人やその関係者とのつながりは必ずしも強いものとは言えず、著者はそうした人のつながりに課題を見ています。
第4章は南太平洋の国々。パプアニューギニア、フィジー、サモアといった国がとり上げられています。
ただし、パプアニューギニアに関してはほぼ今村均の話で、著者の日本陸軍の研究者としての側面が前面に出てきています。
フィジーとサモアについては温暖化の問題などに触れられていますが、重点的に語られているのは中国の進出と「海洋の自由」の話です。
第5章は「揺れるアジア」というタイトルで、ミャンマー、ベトナム、東ティモール、タジキスタンがとり上げられています。
ミャンマーの部分では、新潟の国際大学でミャンマーの軍籍をもっている行政官を受け入れていることに対する批判について触れ、次のように述べています。
ミャンマーの学生はとても先生を尊敬している。軍人はとても優秀である。彼らを日本に招かなければ、かれらはたとえば中国で勉強するだろう。日本にとってどちらがよいか、自明ではないだろうか。(162p)
さらにアウン・サン・スー・チーと会談した際には、「私は、日本におけるかつての民主党政権が功を焦って失敗したことにふれ、慎重に進められることを期待すると述べた」(167−168p)とのことです。
ベトナムの部分では、ベトナムにおける法整備への支援と、明治日本でのボアソナードの業績が重ねられる形絵論じられています。
東ティモールでは現在の国づくりが、明治期の日本の国づくりと重ねられるとともに、ASEANにも太平洋諸島フォーラムにも入っていない東ティモールの不安定な状況が指摘されています。
タジキスタンについての部分では、中央アジアの民族の問題や、タジキスタンの複雑な地形などにふれ、中央アジアにおいて強権的な政治が要請される理由を分析しています。「かつての内戦を知っている人、地理的な統合の困難さを知っている人なら、簡単に独裁を批判できない」(201p)のです。
終章では、まず、2017年に行われたUHC(Universal Health Coverage)フォーラムと、2018年のダボス会議に参加した時の様子が語られています。このような国際会議でが何が話され、どんな意義があるのかということが見えるようになっており、面白いと思います。また、ビル&メリンダ・ゲイツ財団がいずれの会議でも存在感を示しており、こうした大金持ちの動きが国際政治にどのような影響を与えていくのかという部分は興味深いです。
あとは、中曽根康弘が行った1950年の世界一周と、高校に積極的に留学生を受け入れるなど独自の地域活性化をはかっている島根県の隠岐の島の海士町のことが語られています。
このようにこの本は、まずJICAの理事長としての活動の記録であり、JICAの理事長として訪れた発展途上国から見た国際情勢を語る本でもあります。そこがいわゆる大国の動きを中心に世界を語る「地政学」とは一線を画しているところでしょう。
同時にこの本には、「学者」としての北岡伸一と「政治家」としての北岡伸一の2つの側面が現れており、そこも興味深いと思います。
もちろん、学者が現実の政治にコミットすることに対して批判する向きもあるでしょが、昨今の大学を取り巻く状況を見れば、学問の営みが社会から隔絶した形で行われていくというのも難しいわけで、著者のスタンスに反対の人でも、「学問と政治」を考える上で目を通しておいても良いのではないかと思います。