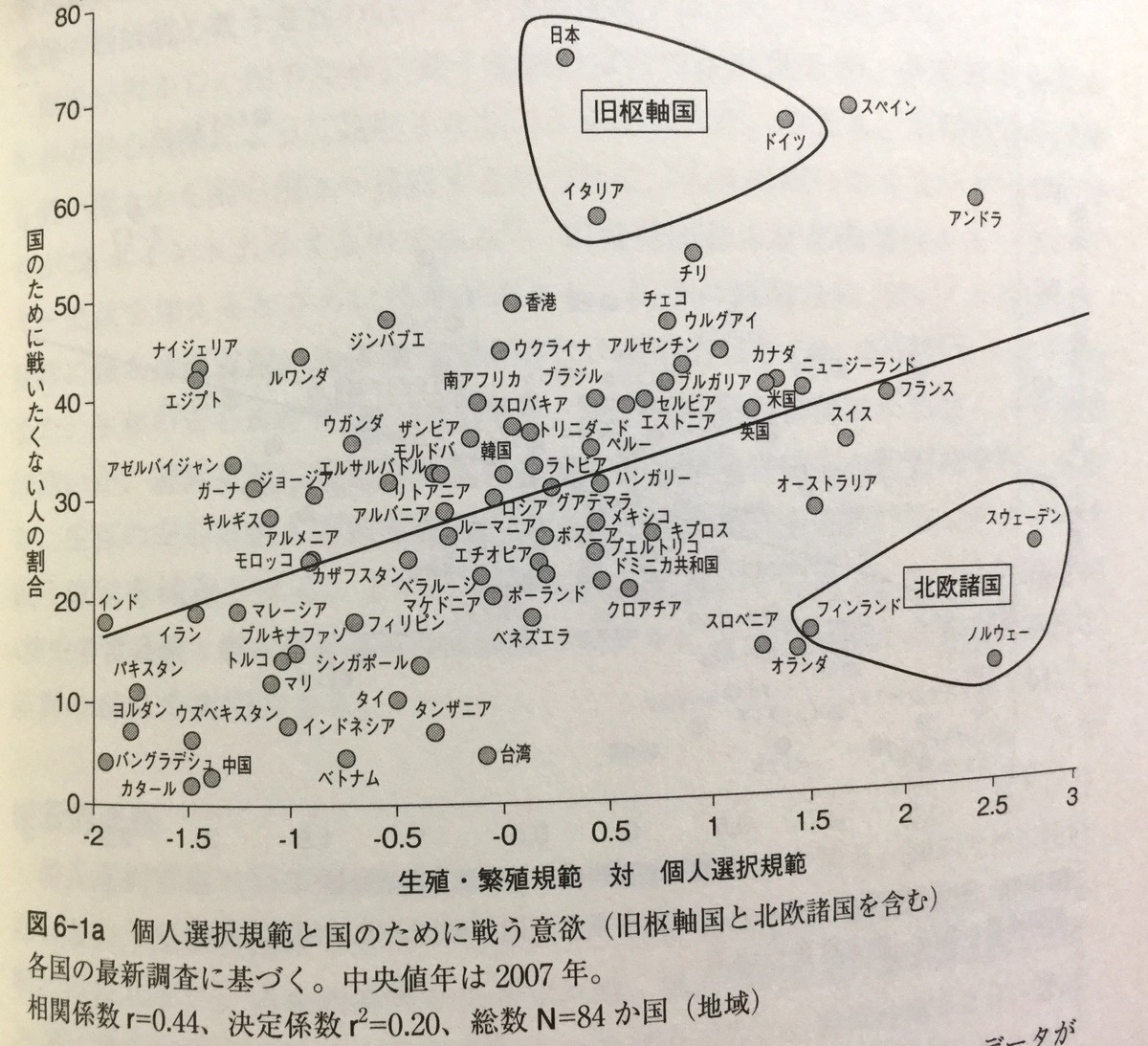それぞれ数多くの論文を発表し高い評価を得ているアセモグルとロビンソンが「経済成長はどのような条件で起こるのか?」という大テーマについて論じた本。読もうと思いつつも今まで手が伸びていなかったのですが、授業でこの本と似たようなテーマを扱うことになったので、文庫版を手に入れて読んでみました。
目次は以下の通り。(第1章〜第8章までが上巻、第9章以降が下巻)
第1章 こんなに近いのに、こんなに違う
第2章 役に立たない理論
第3章 繁栄と貧困の形成過程
第4章 小さな相違と決定的な岐路―歴史の重み
第5章 「私は未来を見た。うまくいっている未来を」―収奪的制度のもとでの成長
第6章 乖離
第7章 転換点
第8章 領域外―発展の障壁
第9章 後退する発展
第10章 繁栄の広がり
第11章 好循環
第12章 悪循環
第13章 こんにち国家はなぜ衰退するのか
第14章 旧弊を打破する
第15章 繁栄と貧困を理解する
付録 著者と解説者の質疑応答
実はこの本を読むのが後回しになっていたのは、以下の山形浩生の上巻の書評を読んでしまったからです。
cruel.hatenablog.com
今回、この本を読んでみたあとも、基本的にはこの山形浩生のものと同じような疑問は残りました。確かにエピソードは面白いのだけど、「経済成長が起きるか否かは制度が包括的か収奪的かによるのだ」というテーゼはやや単純すぎるように思えるのです。
本書はアメリカのアリゾナ州のノガレスとメキシコのソノラ州ノガレスの比較から始まっています。この両地域は気候や地理的条件も、もともと住んでいた住民もほぼ同じにもかかわらず、経済発展では大きな差がついています。この差を説明するのが「包括的制度」と「収奪的制度」の違いです。
著者らのいう「包括的/収奪的」とは政治と経済の両面があって、包括的な政治制度は法の支配と理想としては自由民主主義、包括的な経済制度とは市場経済のしくみで、収奪的な政治制度とは無秩序や権威主義的な独裁体制、収奪的な経済制度とは奴隷制、農奴制、社会主義の計画経済といったものになります。
さらに著者らが度々強調するのが中央集権的でなおかつ多元的な権力のしくみです。多元的というならば地方分権ではないかと考える人もいるでしょうが、著者らは一定の秩序がなければ収奪的な経済にしかなりえないと考えています。
本書ではソマリアのケースなどが紹介されていますが、日本史で考えれば戦国時代では日本全体を巻き込むような経済成長はありえず、信長や秀吉による中央集権が必要なんだけど、そうした個人的な独裁はいずれ収奪的にならざるを得ないので、何らかの形で権力の多元化が必要になるといったところでしょうか。
著者らはイギリスの成長は、大西洋貿易が盛んになった時期に他のヨーロッパ諸国とは違って多元的な権力が成立したからだと考えています。
このように、著者らは制度こそが経済発展のキーだと考えているわけですが、第2章では、経済発展を説明するその他の理論、「地理説」、「文化説」、「無知説」を否定しています。
地理説には熱帯における伝染病や農業生産制の低さを理由にするものや、ジャレド・ダイアモンドが主張する大陸の広がり(東西に広がっているか南北に広がっているか)や周囲にいた家畜化可能な動物の数などを理由とするものがあります。
しかし、著者らはこの説ではユーラシアの中でもイギリスが産業革命をリードしたことやアメリカとメキシコの差を説明できないとして退けています。
文化説を否定するのは、日本や中国などの経済発展や、韓国と北朝鮮の格差、15世紀末にカトリックに改宗したコンゴ王・ジョアン1世などの存在です。
アフリカ経済の低迷を説明する時に無知説は一見すると有効に思えますが、実は経済政策に失敗した国でも多くの場合欧米の経済学者がアドバイザーに就いており(ガーナのエンクルマはアーサー・ルイスから助言を受けていた(上巻126p))
こうして「制度こそ決定的なのだ」という結論が導かれるわけで、特に著者らはイギリスの制度を高く評価しています。イギリスにおける財産権の確立や知的所有権制度がイノベーションを生み、産業革命を引き起こしたというわけです。
このあたりは、例えば、ダグラス・C・ノースの『経済史の構造と変化』の説明に近いと思います。というか、本書全体の分析が『経済史の構造と変化』のそれと似ていると思います。例えば、『経済史の構造と変化』の次の部分などは本書の一節だと言っても充分に通じるでしょう。
経済成長には国家の存在が欠かせないが、人が引き起こす経済の衰退は、国家に原因がある。この逆説を考えれば、国家の研究を経済史の中心に据える必要がある。(ダグラス・C・ノース『経済史の構造と変化』49p)
そして、『経済史の構造と変化』がさまざまな経済学の理論を持ち出しながら叙述を進めるのに対して、本書はまるで歴史家が書いた本のように事例の記述を重ねていきます。
アセモグルもロビンソンも実証的な論文を量産している人なので、本書のベースにはさまざまな実証的な研究があるんでしょうけど、本書では読みやすさを重視してなのか、データやグラフをあまり用いておらず、印象的な事例の紹介が中心となっています。ですから、いろいろな反論も思い浮かびます。
例えば、イギリスは名誉革命以降、包括的な制度が確立したから発展したのだと主張していますが、「イギリスの経済成長の要因は、包括的制度のもとでの国内でのイノベーションという要素より海外植民地からの収奪という要素が大きいのではないか?」といった疑問も浮かびます。
また、著者らは短期の経済成長であるならば収奪的な制度のもとでも可能だが(例えば、ロシア革命後のソ連は農村からの収奪によって一定の期間は高い経済成長を示した)、長期は不可能だといいます。
ただ、この短期/長期というのがどのくらいの幅なのかということも問題だと思います。著者らは長期というときにかなりの期間を想定しているようで、それが結局は「イギリスの産業革命に始まった西欧諸国の経済成長のみが歴史上唯一の経済成長である」というような見方につながってしまっているのではないかと思います。
そうなると確かに「自由民主主義以外に経済成長の可能性はない」となるのかもしれませんが、例えば、中国の宋代の経済成長やイノベーション(羅針盤、火薬、活版印刷術などの発明があった)は、単なる収奪にはとどまらないかなりの長期に渡ったものと見ていいのではないかと思いますが、著者らは「中国は絶対主義的の国であり、宋の成長は収奪的制度によるものだった」(上巻370p)と冷淡です。
ここはK・ポメランツ『大分岐』などでも指摘されているように、もう少し18世紀初めまでの中国の経済力というものを評価してもいいのではないかと思います。
そして、やはりこの本の今後の影響力の行方というのも、やはり今後の中国の姿に関わっているのだと思います。
中国は少なくともここ25年ほどは高成長を続けています。もちろん、今までの成長は先進国で生み出された技術を移転し、農村の余剰労働力を活用した成長で、収奪的な政治制度の上でも予想できる成長だと言えるかもしれません。これについて著者らは次のように述べています。
中国の場合、遅れの取り戻し、外国の技術の輸入、低価格の工業製品の輸出に基づいた成長のプロセスはしばらく続きそうだ。とはいえ、中国の成長は終わりに近づいているようでもあり、とくに中所得国の生活水準にいったん達したときには終わると見られる。(下巻300p)
しかし、近年の中国ではIT関連を中心にイノベーティブといっていい動きが起きています。中国経済の成長が減速するというのには同意なのですが、それは中国のような収奪的な制度のもとではイノベーションが起こらないからではなく、「一人っ子政策」を長くやりすぎたことによる少子高齢化によってもたらされるのではないかと個人的には見ています(もっとも、「一人っ子政策」の引き伸ばしは民主主義であれば防げたかもしれないので、「「一人っ子政策」の引き伸ばしも収奪的な政治制度のせいなのだ」と言われれば、著者らの理論は間違っていないことになりますが)。
さらに中国政府が非民主的制度を維持しながらビッグデータと監視システムを用いることで「うまく統治する」可能性というのもあって、それは梶谷懐・高口康太『幸福な監視国家・中国』で指摘されています。
付け加えるならば、中国の大躍進政策に関しては、第2章で著者らが否定した「無知説」が当てはまるような気もします。
あれこれと文句を言ってしまいましたが、この本に集められているエピソード、特に経済成長に失敗した国々のエピソードに関しては興味深いものがあります。
例えば、シエラレオネでは1961年に独立しシアカ・スティーヴンズ大統領は鉄道を廃止しました。敵対的な勢力を支持する地域を走っていたからです。さらスティーヴンズは軍も信用できなかったために軍を縮小し、骨抜きにしました。結局、彼はクーデターで権力を失い、シエラレオネは内戦に突入していきます。
グアテマラでは93年にラミレ・デ・レオン・カルピオ大統領に就任し、リチャード・アイトケンヘッド・カスティーリョが財務相に、リカルド・カスティーリョ・シニバルディを開発相に任命しました。彼らは16世紀はじめにグアテマラにやってきたコンキスタドールの末裔で、グアテマラでは未だに22の一族が政治と経済を支配しているといいます。エリートによる収奪体制はそう簡単になくなるものではないのです。
また、民主主義でありながらなかなか政治・経済の両面で安定しないラテンアメリカに関しては次のように評価しています。
ラテンアメリカに誕生した民主主義は、原理上はエリート支配の対極にあり、名実とも権利と機会を少なくとも一部のエリートから再分配しようとするものだが、二つの意味で収奪的体制にしっかりと根差している。第一に、収奪的体制下で何世紀も不公正が続いたせいで、新たに誕生した民主主義体制の下で、有権者は極端な政策の政治家を支持するようになる。(中略)第二に、ペロンやチャベスといった有力者にとって政治がこれほど魅力的で甘い汁に満ちているのは、またしても根底に収奪的制度があるせいであり、社会にとって望ましい選択肢をつくる有効な政党の仕組みがないせいだ。(225−226p)
さらに最後では小さな市場の失敗を改善していこうとするやり方を批判し(このあたりは最近流行のRCT批判なんでしょうね。RCTに関してはアビジット・V・バナジー、エスター・デュフロ『貧乏人の経済学』やエステル・デュフロ『貧困と闘う知』を参照)、対外援助に関してもないよりはマシかもしれないが、有効な援助というのは非常に困難であるとの考えを示しています。
「なぜ、西欧が成功したのか?」というだけであるならば、エントリーの中でも触れたダグラス・C・ノース『経済史の構造と変化』を読めばいいのではないかとも思いますが、「なぜ、多くの国は失敗しているのか?」ことに関してはさまざまな示唆を与えてくれる本だと思います。
関連エントリー
morningrain.hatenablog.com