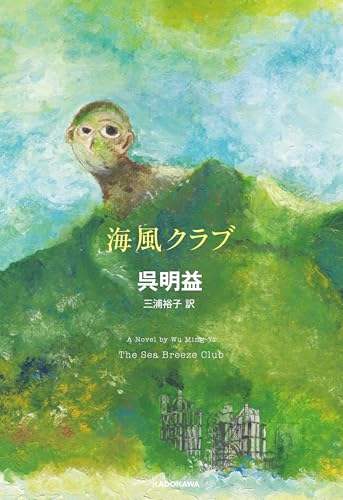なんといってもトランプが代表例ですが、近年の政治では政治経験がほとんどない、あるいはまったくない人物が大統領などの指導者の地位につくケースが増えています。
また、議院内閣制の国においても、新興政党が勢力を伸ばして無視しがたい勢力になっている国も増えています(ドイツのAfDなど)。
こうした状況を本書では「アウトサイダー・ポリティクス」と名付けています。
既存の政治の外側からのチャレンジャーはいつの時代にもいましたが、そうした勢力が短期間で政権に手の届くような位置まで上り詰めるようになったのが近年の特徴と言えるでしょう。
目次を見ればわかるように、さまざまな国の事例が取り上げられており、特にラテンアメリカ、フィリピン、日本のれいわ新選組といった欧米以外の事例が取り上げられているのが大きな特徴だと思います。
以下では、面白かった章だけ簡単に紹介していきますが、現代の民主主義を考えるうえでの重要な知見が詰まっている本になっています。
目次は以下の通り。
はじめに アウトサイダーの時代なのか……………水島治郎
第Ⅰ部 現代政治をどう見るか
第一章 欧州ポピュリスト政党の多様性――概念設定と比較分析(古賀光生)
第二章 西ヨーロッパにおける自由化・市場化の進展と反移民急進右翼政党の「主流化」
――世紀転換期の民衆層急進化の政治史に向けて(中山洋平)
第三章 「アウトサイダー」時代のメディアと政治
――脱正統化される「二〇世紀の主流派連合」(水島治郎)第Ⅱ部 転回するヨーロッパ政治――既成政治の融解
第四章 英国における左右のポピュリズムの明暗
――問われる統治力と応答力(今井貴子)
第五章 右翼政党「ドイツのための選択肢(AfD)」の「主流化」
――若者と旧東ドイツにおける支持とその背景(野田昌吾)
第六章 アウトサイダーのジレンマ
――イタリアにおける五つ星運動の政治路線(伊藤武)
第七章 フランスから見みた「ヨーロッパの極右・ポピュリスト政党」(土倉莞爾)
第八章 鼎立するベルギーのポピュリズム(柴田拓海)
第九章 福祉の代替か、アートの拠点か、犯罪か
――オランダにおける空き家占拠運動の六〇年(作内由子)第Ⅲ部 環太平洋世界はいま――交錯する新旧の政治
第一〇章 トランプ派の「メインストリーム化」と民主党の「過激化」?
――二〇二四年アメリカ大統領選挙の分析(西山隆行)
第一一章 なぜラテンアメリカの人びとは「異端者」を選ぶのか?(上谷直克)
第一二章 フィリピン――食いものにされる「変革」への希望(日下渉)
第一三章 れいわ新選組を阻む壁
――日本の左派ポピュリズム政党の限界(中北浩爾)
第一四章 ポピュリズムへの防波堤としての参議院
――郵政民営化・日本維新の会・希望の党と第二院(高宮秀典)おわりに……………水島治郎
第2章・中山洋平「西ヨーロッパにおける自由化・市場化の進展と反移民急進右翼政党の「主流化」
これは論争的で面白い論考。急進右派支持の理由には経済説と文化説があり、マスコミとは違って政治学では後者が優勢ですが、「主流化」を考える上では前者も外せないと主張する論文になっています。
経済説(急進右派の支持層はグローバル化の敗者)が否定されるのは、これを肯定すると既存の欧州の緊縮・市場化路線を否定しなければならないからではないかと著者は考えており、そこに一種のバイアスを見ています。
ちなみに本章の1つの仮想敵が中井遼『欧州の排外主義とナショナリズム』であり、経済説がいくら論破しても蘇ってくる「ゾンビ仮説」などとは言えないということを主張するものです。
また、この流れで出てくる注1の次の記述は興味深いですね。
幸か不幸か、この文脈は日本には全く当てはまらない。言うに足る反移民(排外主義)急進右翼政党が(これまでのところ)存在していないこと以上に、膨大な国内貯蓄を食い潰すまでは無制約に財政赤字を積み上げて、市場化や(相対的に緩やかな)緊縮に伴う民衆層の痛みを和らげる政策を打ち続ける、という、(コロナ期を除く)この40年の西ヨーロッパではおよそ現実的ではない選択肢を実際に採りえたからだ。(50p)
第3章・水島治郎「「アウトサイダー」時代のメディアと政治」
医者や弁護士と比べてジャーナリストや政治家への信頼が下がっているのは後者が「半専門職」だからだという指摘が興味深い。
20世紀は主流メディアや政党に入らなければ活動ができないため、それが一種の資格となり「専門職」のような形で機能していましたが、ネットの普及などによって情報発信のための資本や、政治活動のための中間組織へのアクセスなどが必須ではなくなり、ジャーナリストや政治家の専門職性が薄れたと指摘しています(政治家については特に比例代表制をとる国ではこの傾向が強くなる)。
第4章・今井貴子「英国における左右のポピュリズムの明暗」
近年の英国政治ではファラージが移民問題や反EUでイシュー・オーナーシップを握り続け、自らの政治目的を実現させる一方で、EU離脱の責任は全部保守党が背負うことになったと指摘しています。
イギリスでは、ポピュリズムの嵐が吹き荒れたあとに保守党の一方的な敗北によって政権をとった労働党のスターマーは明確に反ポピュリズム的な立場を打ち出していますが、このスターマー政権がうまくいくかどうかは今後の先進国の政治を見るうえでも参考になりそうです。
第5章・野田昌吾「右翼政党「ドイツのための選択肢(AfD)」の「主流化」」
AfDの東独地域での強さについて単純な経済格差だけではなく、資産面での格差、各界の指導的地位における東出身者の過小代表といったことが指摘されていて興味深いです。
アウトサイダー政党が政権入りすることで難しい立場に立たされることをイタリアの五つ星運動の盛衰を追いながら分析した論考。五つ星運動の左寄りの経済政策に他党が追随すると、差異化のために急進的にならざるを得なかったことをマニフェストの分析などを通じて明らかにしています。
五つ星運動はイデオロギー色の薄いポピュリスト政党であり、アウトサイダーだった時期は他党の位置を考えながらさまざまな政策を打ち出して差異化に成功していましたが、政権に入ると逆に政策争点を主導する地位を奪われ、インサイダーとしての負の遺産を抱えることになったしまったと。
第9章・作内由子「福祉の代替か、アートの拠点か、犯罪か」
オランダにおける空き家占拠運動についての論考。政治というよりも社会運動の話という感じで、本書の中ではやや異色な論文ですが、一時はお墨付きを与えられた空き家占拠運動が住宅政策の市場化によって退潮したのは興味深いです。
70年代後半以降のいわゆる「新自由主義」的な動きは、効率化や経済成長のためということに加えて、行政のやっかない問題を切り離したいという思いが原動力になったんでしょうね。
第10章・西山隆行「トランプ派の「メインストリーム化」と民主党の「過激化」?」
本人にそれほど強い立場があるわけではないがリベラルなカリフォルニアを地盤にするがゆえにリベラルに振る舞い、それゆえにそれに反する政策を出すと反発されるハリスのジレンマについての記述が興味深いです。
日本にいるとわかりにくいですが、アメリカの有権者の中にはハリスを「極端だ」と考える人がトランプを「極端だ」と考える人と同じくらいいます。そしてトランプとハリスの双方を「極端だ」と考える人の67%がトランプに投票したというのです。(230p)
第11章・上谷直克「なぜラテンアメリカの人びとは「異端者」を選ぶのか?」
ポピュリズムの伝統を持つラテンアメリカにおけるアウトアイダーについて。もともと政治の属人化が進み、伝統的な政党システムが崩壊しているラテンアメリカではそもそも現職が弱く、つねにアウトサイダーが参入しやすい状態にあります。。
さらに近年に関してはコモディティブームで豊かになった新しい中間層がブームの終焉で不安定化し、相対的剥奪感を抱いていることがボルソナロやミレイの当選の背景にあるのではないかと分析されています。
第12章・日下渉「フィリピン」
フィリピンではクライエンテリズムが地方選挙では根強く残る一方で、全国区の正副大統領選や上院選ではそれが効かず、属人的な政治が行われてきました。
エストラダに代表される貧困層向けのポピュリズムは経済成長とともに下火になりましたが、その経済成長は海外就労や先進国からのコールセンターなどのアウトソーシングによって支えられており、単身赴任、感情労働、アメリカの時差に合わせた労働などかなり労働者に無理がかかっているとのことです。
また、中間層の規律や秩序を重んじる権威主義的志向が、ドゥテルテやマルコスJr当選の背景にあるのではないかとも指摘されています。
第13章・中北浩爾「れいわ新選組を阻む壁」
政治学者による政治家山本太郎論でもありけっこう新鮮。山本太郎の政治遍歴をたどりながら、れいわ新選組の躍進と、ぶち当たっている限界について論じています。
最後の山本太郎が小沢一郎とともに国民民主→立憲民主に移っていたらコービンやサンダースのような存在になっていたか? という問いは興味深いですね。
相変わらず「ポピュリズム」は政治の世界のバズワードですし、さまざまな形で論じられていますが、どうしても分析対象を低く見る形になったしまいやすいです。
その点、本書では「アウトサイダー」という言葉を使うことで、よりフラットな形で現代の政治現象を捉えることができているのではないかと思いました。
自分に興味のある国についての論考を読むだけでも十分に得るものがあるかもしれませんが、各国の事情をそれぞれ掘り下げることで見えてくるところもあります。
個人的にはポピュリズムの瞬間最大風速のピークを超えた感のあるイギリスとイタリアの政治の今後に注目したいと思いましたね。